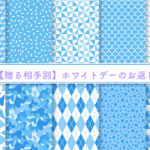「鏡開きは1月11日!」と言いたいところですが、実は地域によってズレがあるんです。(ややこしい!)
今回は、場所ごとの鏡開きの日にち、この日に鏡餅を食べる理由、なんで「鏡餅を切る」とは言わず「開く」というのかについてご紹介します。
鏡開きはいつ?

鏡開きは一般的には1月11日。1並びで縁起がよさそうな日ですよね。
ところが、
松の内(正月飾りを飾る期間)の期間や鏡開きの日は地域によって違うんです。
| 松の内の期間 | 鏡開き | エリア |
| 1月7日まで | 1月11日 | ほとんどのエリア |
| 1月15日まで | 1月15日 | 関西エリア |
| 1月15日まで | 1月20日 | 関西エリア |
鏡開きの日がバラバラな理由
鏡開きは、元々1月20日(松の内は1月15日まで)とされていました。
ところが、20日は三代将軍「徳川家光」の月命日と重なってしまったので1月11日に変更。
関東周辺では11日で定着しましたが、関西方面では定着したりしなかったりいう感じでバラツキが出たようです。
ちなみに、京都や近畿の一部では1月4日に鏡開きをするところもあるそう。
なんでかは不明ですが、手作りした鏡餅の日持ちを考えると4日は一番妥当な気がしますよね。
鏡餅はなぜ開くというの?

それは「切る」とか「割る」という表現が忌み言葉(縁起の悪い言葉)だから。
実際、鏡餅は年神様が宿る場所なので刃物で切ることはせず、手や木づちで割るのがふつう。
ただ、「割る」という言葉を避けたいので「開く」に言い換えています。
「開く」は末広がりのイメージで非常に縁起のいい言葉。
祝宴で樽酒を割ることも「鏡開き」と呼ばれています。(酒樽の蓋は「鏡」と呼ばれている)
鏡餅を食べる意味

お正月にお供えした鏡餅には、家にお迎えした年神様が宿ると信じられています。
年神様が滞在するのは松の内の期間。(1月1日~7日or15日)
年神様をお見送りした後に鏡餅を食べるのは、年神様の恩恵を頂いて新年の健康や幸せを祈願するためです。
鏡餅の「鏡」は三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」に由来した縁起物で、鏡には「円満」の意味も。
その鏡(円満)を開く(末広がりの意味)鏡開きは超ラッキーアクションです。
長寿を願う意味も
鏡餅には長寿を願う意味も込められています。
なぜかと言うと、固い鏡餅は歯が丈夫じゃないと食べられないから。(手作りした鏡餅はかなり固い)
という意味合いから、鏡餅を食べて健康と長寿を願う「歯固め」の儀式も大昔から行われていたそうです。
おわりに
日本の風習は地域によって違うことが多くて興味深いです。
私の地域の鏡開きは1月11日。それ以外の日に鏡開きをする場所があるなんて思いもしませんでした。
鏡開きに鏡餅を食べるのは年神様の恵みを頂くラッキーアクション。
お雑煮やぜんざい、あられなどにして、感謝しながら味わいたいですね。